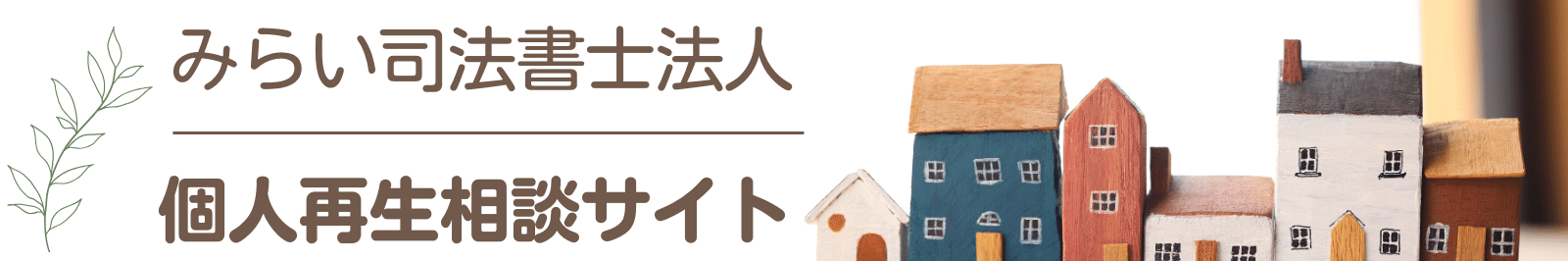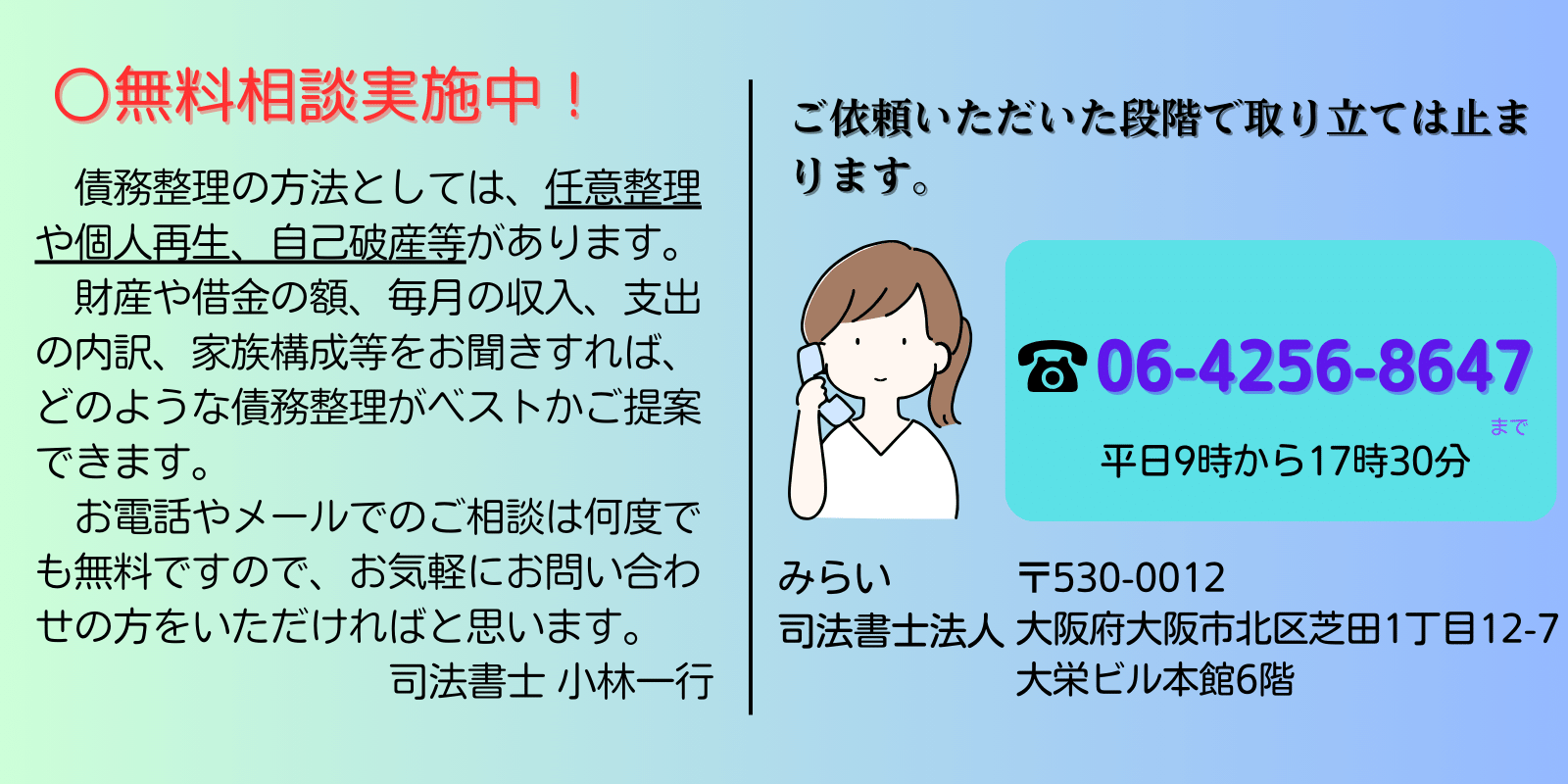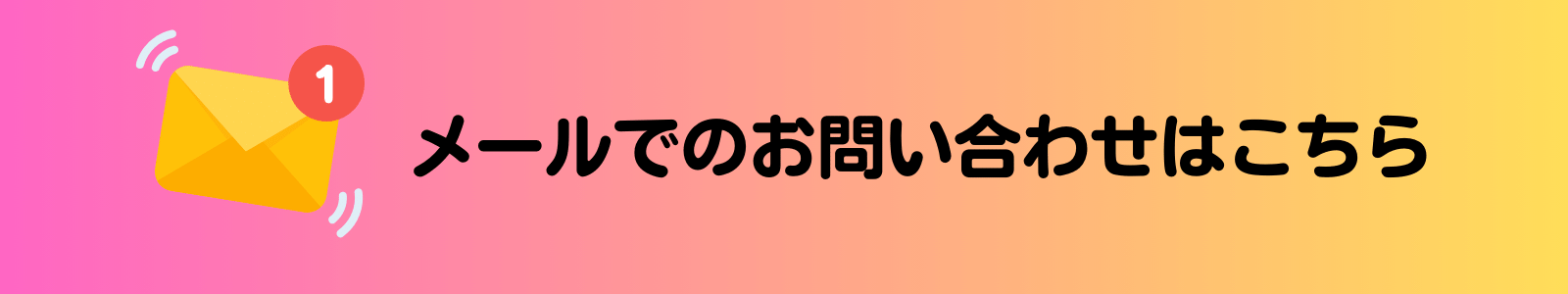個人再生を申請するときの債権者が消費者金融などの業者だけとは限りません。
友達や家族、勤務先など、知人から借りているケースもあります。
このコラムではその際の個人再生での問題点について解説いたします。
(このコラムで個人再生を申請する人を以下「申請者」とします。)
1、知人からの借金を除外することの問題点
まず、この知人からの借金はなにが問題かを説明いたします。
申請者からすると借りたものはちゃんと返したいという思いが当然あります。しかし個人再生が認可されると各債権者の申請者への債権は通常大幅に減額となります。
そうすると貸したお金(貸金)が減って泣くのは債権者です。
そのため、知人が債権者の場合、その人達に迷惑をかけれない事を悩んでしまうのです。
2、知人からの借金と債権者平等の原則
それでは、知人からの借金のみ除外して、今までどおり知人へ返済できないでしょうか。
これができれば、知人には迷惑をかけません。
しかし残念ながら、個人再生では一部の債権者のみを除外することは認められていません。
なぜなら個人再生の手続きでは債権者平等の原則という重要な理念があるからです。
例えば消費者金融Aから600万、友人Bから700万円の借金があるとします。
この場合、個人再生が認可されると、Aの借金は5分の1の120万円に減額されます。しかしBの借金は個人再生で除外しているので700万円のままです。
これはAからすれば到底納得できないでしょう。なぜうちが貸したお金は大幅に減らされてしまうのに、Bの貸金は一切減らないのかと。業者であろうがなかろうが貸しているお金は返してもらえると期待しているのは同じです。
そのため、個人再生では債権者間の不平等を許さないという仕組みをとっているのです。
その結果Bからの借金額も債権者の名簿(一覧表)に載せて裁判所に提出する必要があります。
Bから恨まれることになってしまいますが、それは仕方がありません。それよりも申請者の生活を立て直して借金を完済させることの方が重要です。
3、知人からの借金をなんとかして除外できないか。
しかしそうは言ってもどうしても知人に迷惑をかけたくないという場合もあります。そのため以下は非常手段ですが、知人に迷惑をかけない方法をいくつかご紹介いたします。
(1)知人への借金を誰かに肩代わりしてもらう。
例えば友人Aから30万円借りているとします。申請者の父がBとします。この場合、Bに頼んでBがかわりにAに30万円を返済します。そうするとAから申請者への債権30万円はBに移転します。その結果Bが債権者となります。そのため、あとはBを債権者として扱えばOKです。
注意点ですが、Bからまず申請者にお金をわたして、申請者からAに返済するのはNGです。
申請者自身の返済とみなされて、債権者平等原則違反を問われる可能性があります。
Bから直接Aに振込み等の方法で返済するようにしてください。
(2)申請者自身が返済してしまう。
さらに少しグレーなやり方ですが、申請者自身が知人に返済してしまう方法もあります。下記の事例をもとに検討します。
各債権者の債権額の内訳
| 債権者名 | 申請者への債権額 |
| 消費者金融A | 250万 |
| クレジットカード会社B | 250万 |
| 勤務先C | 200万 |
借金は財産の額までの減額が限界
上記の場合、合計の債権額(借金)は700万円です。
そして個人再生認可で、700万円の借金は原則5分の1の140万円まで減額されます。
しかし減額後の借金の額は、財産の総額を下回ってはいけないというルールがあります。
そのため、借金の額の5分の1と財産の総額を比較して高い方までしか減額されません。
仮に申請者に財産がなければ、700万円の借金は5分の1の140万円まで減額されます。しかし申請者に200万円の財産がある場合。
この場合は、140万円(借金5分の1)より200万円(財産の総額)の方が大きいです。そのため、個人再生認可により700万円の借金は200万円までしか減額されません。
債権者からすれば、申請者が持っている財産分くらいは返済してほしいとの期待があります。(これを清算価値保証の原則といいます)
意図的な財産変動は認められない
この債権者の期待は重要です。そのため申請者が財産を意図的に減らしたとしても、その財産は個人再生ではまだ持っているものとして計算されます。
例えば、申請者がCを優遇して200万円を返済すると、申請者の200万円の財産はなくなります。しかし個人再生ではまだ200万の財産を持っているものとして扱われるのです。
その結果、個人再生認可後の借金の額は下記となります。
Cは申請者から200万円の返済をしてもらったので債権者ではなくなります。そしてAとBの借金を足した合計500万円は原則5分の1の100万円となるのではなく、総財産として認定される200万円までしか減額されません。
申請者は最初にCに200万円を返済しているため、結局もともとあった700万円の借金は実質的には400万円までしか減額されないということになってしまいます。
Cに先に返済しなければ、200万円まで減額されることと比較してこれは大きな損失といえます。そのため先に一部の債権者に返済をするという手法は損害が大きすぎるためお勧めできません。
(3)知人からの借金がある場合は、任意整理でいく。
個人再生は裁判所へ申請する法的な債務整理手段です。
これに対して弁護士や司法書士が各債権者と任意で交渉をして毎月の返済額や金利を見直してもらう任意整理という債務整理手段もあります。
この場合は債権者との任意の話し合いですので、債権者平等の原則は働かず、一部の債権者を除外することも可能です。そのため、知人の債権を除外したい場合は任意整理でいけばよいことになります。
しかし元金が一部カットされる個人再生と比較して、任意整理の場合は通常元金のカットまでは債権者も応じてくれません。
そのため、毎月の返済額は個人再生ほどは減らない点に注意が必要です。
(4)債権を放棄してもらう
ちなみに知人の中には申請者の再起に協力するために債権を放棄してくれる人もいます。
友人ですとなかなか難しいですが、親が債権者の場合は子供のために放棄してくれることも多いでしょう。
その場合は債権放棄書に一筆署名をもらえば、債権者ではなくなります。
その結果、個人再生の債権者名簿にも放棄してくれた知人は債権者に載せる必要はありません。